2025.06.04
第3回
株式会社シンクハピネス / 代表取締役 糟谷 明範氏
空気を変えよう。

だれもが直面する可能性のある身内の介護や看護。
関心があるけどまだ相談するほどじゃない、漠然とした不安があるけど、何を相談したらよいかわからない。そんな人がふらっと立ち寄れる場が府中の片隅にある。
医療や福祉の看板は掲げない
京王線多磨霊園駅の駅前商店街にある「カフェ&コミュニティスペース FLAT the town stand」(以下、フラットスタンド)。府中市を中心に看護・リハビリテーション事業として「LIC訪問看護リハビリステーション」を展開する株式会社シンクハピネスのコミュニティ事業部が運営するカフェだ。ただずまいはおしゃれだが、店内には、チラシや張り紙がひしめいていて、ちょっと賑やか。ここは、介護やリハビリ、体の不調などの相談に乗り、必要に応じて施設の紹介などもする相談所になることがある。

「カフェでは、オープン当初からたくさんのイベントを開いて、その中で医療や福祉に関わるものもありました。なので、ご近所の方は私たちが何をしているか知っていると思います。でも、あえてこちらから『相談受け付けます』と看板を掲げることも、お客さんに『お困りごとはありますか』なんて話しかけることもしていません」
そう語るのは、代表取締役の糟谷明範氏。行政と連携しているわけでもない。フラットスタンドは、知る人ぞ知る、言い方を変えれば、知ろうとしなければなかなか出会う機会のない存在なのだ。
「医療や福祉の専門職は、基本的に困っている方に何かしてさしあげたいと思っている人たちです。そのため、よかれと思って『悩みごとはありませんか』なんて聞いたり、情報をあれこれ伝えたりしがちなのですが、人によってはありがた迷惑なこともありますし、そもそも初めて会った人にいきなり深刻な相談なんかできませんよね。僕自身もこれまで何度もそう指摘されたり、ときには叱られたりしてきました。結果、こちらからは伝えない、聞かれたら相手の様子を見ながら役に立ちそうな情報を少しずつ伝える、という現在のスタイルにたどり着きました」

コーヒーを飲みながら相談を
フラットスタンドのオープンは2016年。糟谷氏はかつて理学療法士として総合病院に勤めていたが、ある違和感を抱えていた。
「医療従事者は態度が威圧的、患者さんは遠慮して何も言えないという状態で。両者はもっとフラットな関係であるべきではないかと思ったんです」
医療機関の都合が優先され、患者は言いなりで動くしかない。そんな場面を何度も目にした。
「たとえば、僕が勤めていた病院では少しでも多くの患者をこなすために、早期退院を掲げていました。早く自宅に帰ることはとても大事なことですが、自宅で暮らすための準備が整わないまま退院するようなこともあったりして……」
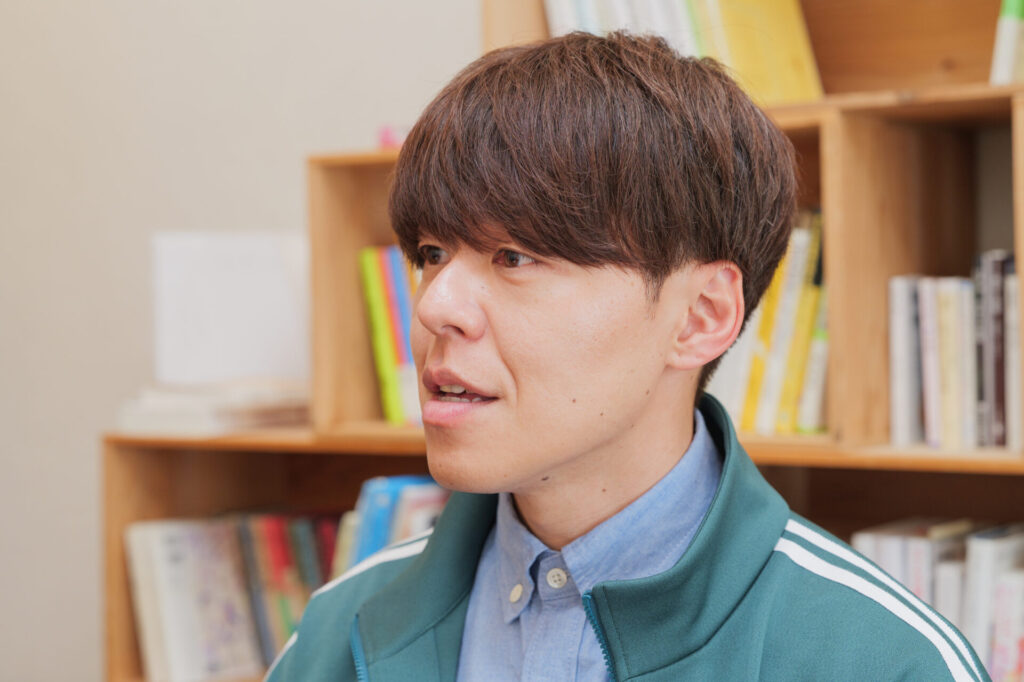
そんなわだかまりに突き動かされて、総合病院を退職。病院の中ではなく、まちや生活の視点から患者さんの暮らしを見つめたい、また自宅でのリハビリテーションの質を確かめたいと、訪問看護ステーションに転職し、経験を積んだ。
「いろいろな訪問看護関連の事業所を見ましたが、正直、家族や友人など大切な人に紹介したいと思えるところが限られていて。ならば、自分でつくるしかないと思いました」
そして2014年、シンクハピネスを立ち上げた。こだわったのは、カフェを設けることだ。
「例えば訪問看護サービスを受けたいとなっても、仕組みが複雑で情報が少なく、選択肢も限られています。介護保険制度が始まってすでに25年が経ちましたが、いまだに受けたいサービスを自分や家族で選べる状態にはないのです。そこで、コーヒーでも飲みながら、必要があれば気軽に専門職に相談ができる、そんな場をつくりたいと思いました」
それがフラットスタンドになった。
糟谷氏は、カフェに立ちながら「一人の人」として、まちに溶け込むことも重視している。
「こちらが医療や福祉の専門職とわかると、根ほり葉ほり聞かれるんじゃないかと警戒されたり敬遠されたりしてしまいます。だから、僕たちがフラットスタンドにいるときは、あくまでもカフェのスタッフであろうとしています」
もっとも、カフェの客としてやってきた高齢者が、話の流れで「電球が切れたけど交換できない」とこぼして、「じゃあ交換に行くよ」と請け負うなんてこともよくあるという。そうやってまちの人たちと日ごろから交流することで、その人の生活の様子もイメージしやすくなる。だからこそ、いざ相談があったときには、より的確な提案ができるのだと、自信をのぞかせる。
「6年ぶりに来店されたお客さんが、『実は母親の具合が悪くなって』と僕たちに相談される。そんなことがよくあります。相談したいタイミングも内容も人それぞれ。同じ人でも、昨日と今日では状況が異なることだってあります。医療や介護には科学的に正しいことがあり、専門職として一流であり続けることを自分自身にもスタッフにも求めていますが、だからといって押し付けるのではなく、一人ひとりの変化に寄り添いながら、その人にとっての“いい感じ”を一緒に探り、“いまのしあわせ”をつくっていけたら、と思っています」
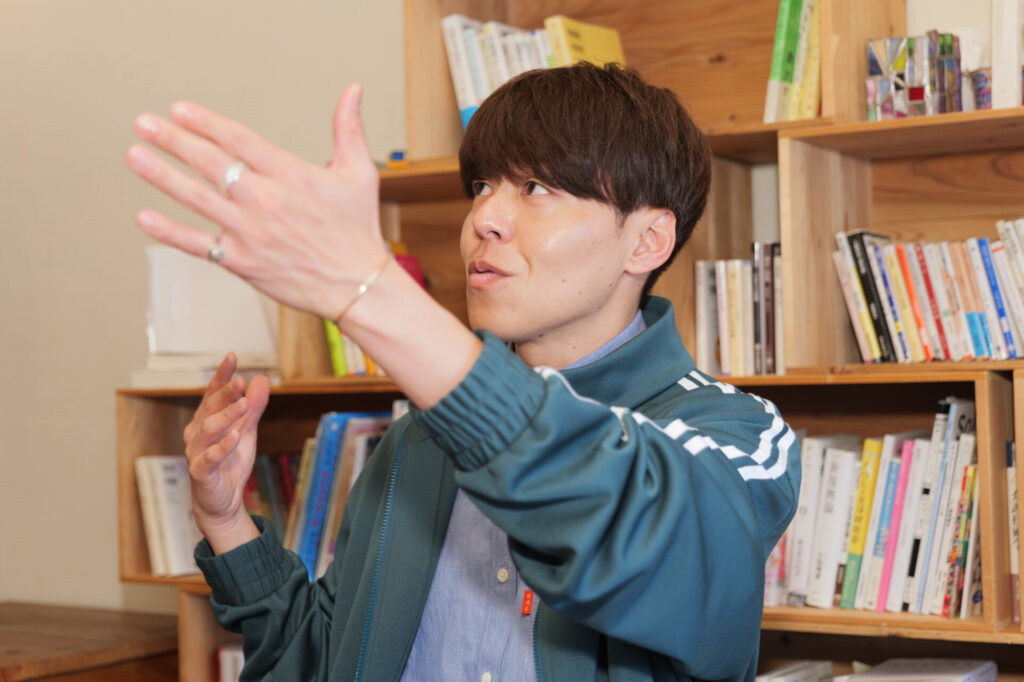
選択肢を増やしたい
フラットスタンドの雰囲気が知りたいと思ったら、6月8日(日)に行われる「たまれ万博」をのぞいてみるのもいい。
「たまれ万博」とは、フラットスタンドと、その並びにある2棟のアパート「糟谷コーポラス」「第二糟谷コーポ」及びアパート前のスペースに、焼き菓子やアクセサリー、花などの販売や染物などのワークショップ、キッチンカーが出店する、いわば文化祭。出店者は府中以外の地域からも広く集まるのだが、それこそが狙いだと糟谷氏は語る。
「僕たちが事業として取り組んでいることは、制度という枠に入らない人たちをどうサポートするかということなんです。もちろん、僕たちだけではすべての人は救えません。それよりも、それぞれがそれぞれの場所で医療や福祉を考え、それぞれの方法でなんとかしてほしい。その意味で、たまれ万博は、『あそこだけ、外から人がいっぱい来て盛り上がってるよね。空気が違うよね』と注目されることで医療や福祉を考えるきっかけづくりにしてもらう、僕らなりの一つの手法でもあるのです」
糟谷氏が今後目指すのは、医療や福祉の助けを必要としている人たちのために、サービスの選択肢を増やすこと。

「医療や福祉の対象は介護やリハビリ以外にも、子育てやジェンダー、貧困などたくさんあります。それらに対応したくても、いまの僕らだけではできない部分もある。だからこれからは各分野の専門家たちとかかわりをつくり、ぜひお力をお借りしたいと思っています」
社会は変えられないが、空気は変えられる。そう信じて活動する糟谷氏のまわりの空気は、すでに変わり始めているようだ。

プロフィール
糟谷 明範氏(かすや あきのり)
株式会社シンクハピネス代表取締役。理学療法士。学生時代はサッカー部。日焼けで真っ黒だったが、「今は日焼け止めを塗っている」。シンクハピネスやフラットスタンドの軌跡をたどりながら「つながり」について考察したWEBメディア『ブルーブラックマガジン』での連載をまとめた書籍が2025年9月出版予定。
株式会社シンクハピネス
ミッションに「“いま”のしあわせをつくる」、ビジョンに「わたしとここで暮らす人と医療と福祉がいい感じになっている社会をつくる」を掲げ、LIC訪問看護リハビリステーション(訪問看護)、LIC居宅介護支援事業所(居宅介護支援)、the town stand FLAT(カフェ&コミュニティ)を展開。フラットスタンドでは現在もいろいろなワークショップが開催されているが、今後はサークルなどに定期的にスペースを貸し出す「公民館化」も計画中。
ライター
岩田 正恵・藤田 覚/futuretune
編集部より
「府中が好き」は、ハッピーカーズ府中店 が運営する地域メディアです。
私たちは地域企業として、事業活動だけでなく、 府中がより良い街であり続けるための取り組みに関わり続けたいと考えています。
本記事は、その活動の一環として、府中で活躍する人や想い、取り組みを記録し、発信しています。
